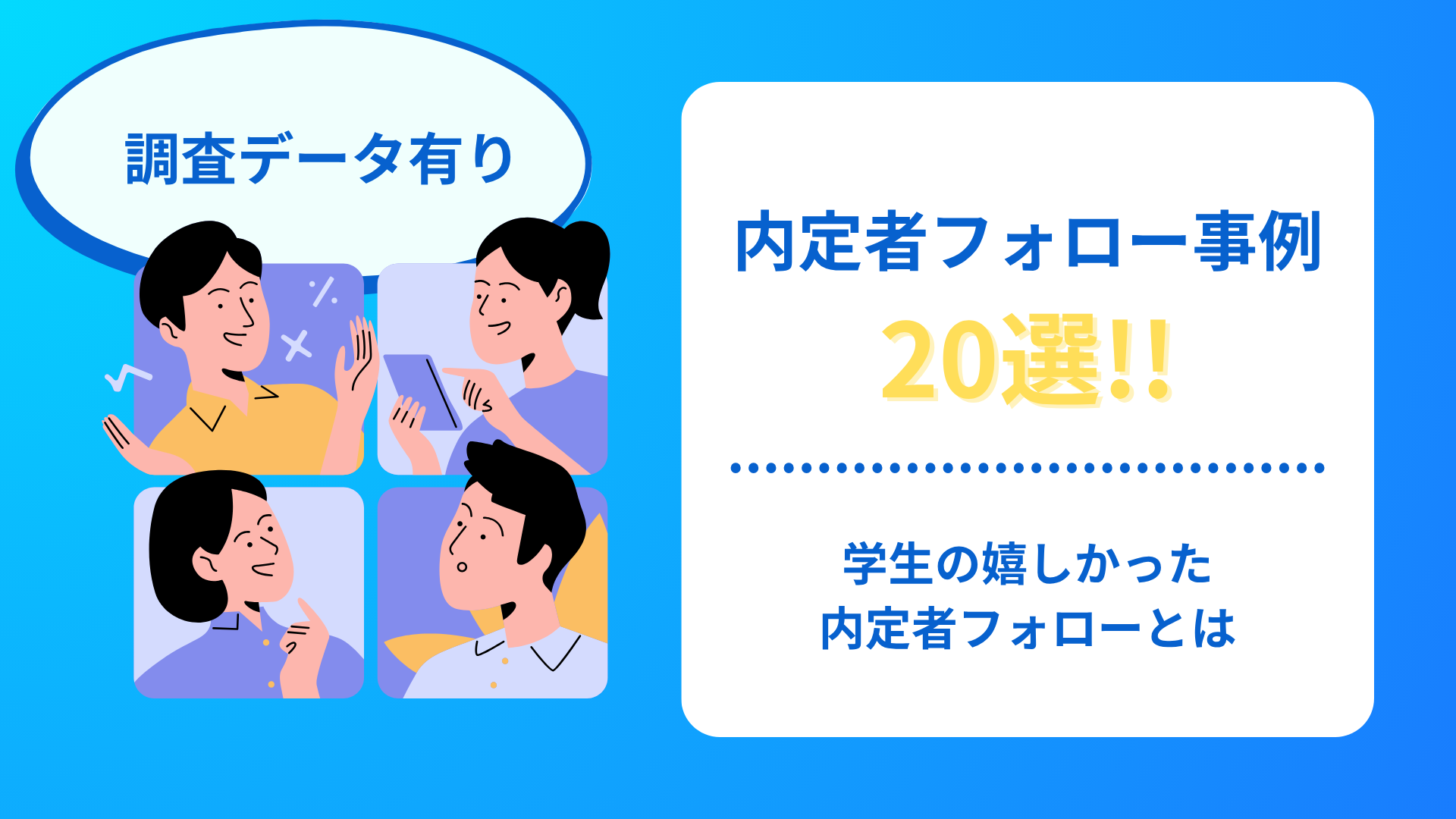内定者フォローとは?
学生の本音から導く内定者フォローの「次の一手」とは?
内定者フォローとは、企業が内定を出した学生や転職希望者に対し、入社までの期間に行う様々なサポート活動を指します。具体的には、面談や懇親会、研修などを通じて、内定者が抱える不安や疑問を解消し、企業への理解を深めてもらうことを目的としています。これにより、入社へのモチベーションを高め、スムーズな入社を促進するだけでなく、内定辞退や早期離職の防止にも繋がります。本記事では採用競争が激化する現代において、内定者フォローが不可欠な施策となっている要因や具体的な事例について網羅的にご紹介いたします。
企業が内定者フォローを行う3つの目的
まず、企業が内定者フォローに力を入れるのには、大きく3つの目的があります。
内定辞退の防止
1つ目は、内定辞退の防止です。採用活動には多大な時間とコストがかかります。苦労して獲得した内定者が辞退してしまうことは、企業にとって大きな損失です。内定者フォローは、内定者が他社へ流れることを防ぎ、自社への入社意欲を維持・向上させるための重要な手段です。
入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職を防止する
2つ目は、入社後の早期離職の防止です。入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチが生じると、早期離職に繋がる可能性が高まります。内定者フォローは、入社前に企業文化や実際の業務内容、職場の雰囲気などを具体的に伝えることで、内定者の期待値と現実とのギャップを埋める役割を担います。これにより、入社後の戸惑いを減らし、スムーズな適応を促すことで、早期離職のリスクを軽減することができるでしょう。
入社前の不安解消と動機形成
3つ目は、入社前の不安解消と動機形成です。内定者は、入社後の仕事内容、職場の人間関係、スキルアップの機会など、様々な不安を抱えていることがあります。内定者フォローは、これらの不安を事前に解消し、安心して入社を迎えられるようサポートします。また、企業理念やビジョン、事業の将来性などを伝えることで、内定者の入社への期待を高め、働くことへのモチベーションを形成する効果もあります。
内定辞退率は上昇傾向?知っておきたい最新の採用動向
近年、採用市場は売り手市場の傾向が続いており、内定辞退率は上昇傾向にあります。株式会社マイナビの「2024年卒 学生就職モニター調査 7月の活動状況」では、学生の平均内定保有社数が2.6社(2023年7月時点)と高水準を維持しており、学生が複数の選択肢を持つことが常態化しています。
このような状況下では、企業は内定を出した後のフォローをより一層強化し、内定者が自社を選び、安心して入社できるような環境を整えることが、優秀な人材確保の鍵となります。内定者一人ひとりに寄り添い、個別の不安や疑問を解消していくきめ細やかな対応が、今後の採用競争を勝ち抜く上で不可欠です。
参照:マイナビ「2024年卒 学生就職モニター調査 7月の活動状況」
┗▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼
なぜ内定辞退は起こるのか?内定者が抱える不安
売り手市場の傾向が続くため、一定の内定辞退はどの企業も経験します。内定辞退はなぜ起こってしまうのかを、内定者が抱える不安と内定辞退に繋がってしまう理由から紐解きます。
まず、内定辞退が発生する背景には、内定者が抱えるさまざまな不安が深く関係しています。内定を獲得し、ひと段落ついたように見えても、多くの内定者は入社に向けて少なからず懸念を抱いているものです。株式会社ラーニングエージェンシーが行った「【内定者1,004人の意識調査】によると、77.2%の内定者が入社に向けて不安を抱えていることが判明しました。
内定者がどのような不安を抱えているのかを理解し、それらを払拭するための適切なフォローを行いましょう。
社風や人間関係への不安
内定者が抱える不安の中でも特に大きいのが、入社後の社風や人間関係への懸念です。
企業説明会や面接だけでは、実際の職場の雰囲気や社員同士のリアルな関係性を完全に把握することは困難です。そのため、「入社してみたら想像と違った」「職場の雰囲気に馴染めるか不安」といった漠然とした不安を抱く内定者は少なくありません。特に、新しい環境での人間関係構築に対する不安は強く、「同期や先輩、上司とうまくやっていけるか」といった心配は、入社への意欲を低下させる要因となります。オンラインでの採用活動が主流となる中で、直接的なコミュニケーションの機会が減少し、入社後のイメージが掴みにくいと感じる学生が増えていることも、この不安を助長しています。
就職先の選択に対する迷い(他に自分に合う企業があるのではないか)
二つ目は、複数の企業から内定を得ている場合、内定者は「本当にこの会社で良いのか」「他にもっと自分に合った企業があるのではないか」といった就職先の選択に対する迷いを抱きがちです。
特に、内定承諾前に他の企業の選考が進行している場合や、さらに良い条件のオファーを受ける可能性を考えると、現在の内定企業への入社を躊躇するケースも少なくありません。このような迷いは、企業への帰属意識が十分に育っていない段階で生じやすく、内定者が他社の魅力的な情報に触れることで、最終的に内定辞退へと繋がる大きな要因となります。企業側は、自社の魅力を継続的に伝え、内定者が迷いなく入社を決意できるようなサポートが求められます。
就職先の選択に対する迷い(社後のキャリアパスが不明確)
内定者が抱えるもう一つの迷いの原因は、入社後のキャリアパスが明確に見えないことです。「入社後にどのような経験を積み、どのようなスキルを身につけられるのか」「将来的にどのようなポジションを目指せるのか」といった具体的なキャリアイメージが湧かない場合、内定者は自身の成長や将来性に不安を感じやすくなります。特に長期的な視点でキャリアを考える内定者にとっては、目先の業務内容だけでなく、数年後、数十年後の自身の姿をイメージできるかどうかが、入社の意思決定に大きく影響します。企業が内定者のキャリアに対する漠然とした不安を解消し、具体的な成長機会やキャリア形成の道筋を示すことができれば、内定辞退のリスクを低減し、入社へのモチベーションを高めることができるでしょう。
┗▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼
なぜ内定辞退は起こるのか?内定辞退につながる主な理由
なぜ内定辞退が起こるのか?という問いに対して、内定者が抱える不安について紹介しました。しかし、内定辞退が起こってしまう背景にはもちろん企業側のサポート不足の要因もあります。
本章では、内定辞退につながる主な理由を2つ紹介します。
他社との比較で魅力が下がる
まず1つ目は、他社と天秤にかけた結果自社の魅力が相対的に下がってしまうことです。
株式会社マイナビの調査によると、内定を辞退した学生の理由として「第一志望の企業から内定を得たから」が常に上位を占めています。これは、学生が内定承諾後も就職活動を継続していたり、複数の内定の中から最終的な意思決定をしたりする過程で起こります。
重要なのは、比較される対象が給与や福利厚生といった条件面だけではない点です。企業の将来性や事業内容、働く社員の雰囲気、キャリアパスの多様性といった、目に見えにくい「魅力」も評価されています。したがって、企業は内定者フォローを通じて、自社の魅力を継続的に伝え、内定者が抱く期待感や入社意欲を維持し続ける努力が求められます。
(参照:株式会社マイナビ:2024年卒大学生活動実態調査 (6月))
連絡頻度の少なさや不信感
2つ目の理由は、連絡頻度の少なさや不信感を与えてしまう事です。内定承諾から入社までの期間中、企業からの連絡が途絶えがちになると、内定者は大きな不安を感じ、企業への不信感を募らせる原因となります。株式会社学情が実施した調査では、内定承諾後に不安を感じた学生のうち、その理由として「企業からの連絡が少ない」ことを挙げる声が多く見られました。特に、数ヶ月にわたって何の音沙汰もない状態が続くと、「自分は本当にこの会社に歓迎されているのだろうか」「忘れられているのではないか」といった疑念が生じ、徐々に入社意欲が削がれてしまいます。このようなコミュニケーション不足は、内定ブルーを加速させ、より頻繁に連絡をくれる他の企業へと気持ちが傾くきっかけにもなり得ます。事務的な連絡事項がない場合でも、定期的に会社の近況を伝えたり、先輩社員からのメッセージを送ったりといった能動的な内定者フォローを行いましょう。
(参照:株式会社学情:[20代専門]転職サイト「Re就活」調査(内定承諾後の不安))
【内定者の本音】データで見る「嬉しかった」内定者フォロー事例
内定者フォローの必要性を感じていただけましたでしょうか?
次に気になるのは、数多くの企業が内定者フォローに注力するなか、本当に学生の心に響き、入社意欲を高める施策とは何かという点です。画一的なフォローでは、かえって内定者の負担になることもあります。重要なのは、内定者が「何を求めているか」という本音に寄り添うことです。実際に複数の調査データを見ると、内定者が「参加して良かった」「嬉しかった」と感じる内定者フォロー事例には共通した傾向が見えてきます。ここからは、内定者のリアルな声やデータを基に、満足度の高い内定者フォローの具体的な内容を5つの切り口から深掘りしてお伝えします。自社の取り組みを見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。
社員とのリアルな交流機会
内定者が最も価値を感じるフォローの一つが、現場で働く社員とのリアルな交流機会です。人事担当者との面接だけでは見えにくい、日常の業務内容や職場の雰囲気、仕事のやりがい、そして時には大変なことまで、社員の生の声を聞ける座談会や個別面談は、入社後の働く姿を具体的にイメージさせ、ミスマッチを防ぐ上で絶大な効果を発揮します。内定者向けの調査でも「社員と話す機会」は常に満足度の高い内定者フォロー事例として挙げられます。大切なのは、企業が一方的に魅力を語る場ではなく、内定者が抱える些細な疑問や不安を気軽に質問できる「対話」の場を設けること。特に、年齢の近い若手社員が参加する座談会は、内定者が本音を話しやすく、よりリアルな情報を得られるため好評です。
┗▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼
同期とのつながりが持てる機会
次に紹介するのは、同期との繋がりが持てる機会の提供です。社会人になることへの期待と同じくらい、新しい環境への不安を抱えているのが内定者の本音です。その不安を和らげ、入社への期待感を高める上で欠かせないのが、同期となる他の内定者とのつながりを育む機会です。食事会のようなカジュアルな懇親会や、チームビルディングを目的としたグループワークなどのイベントは、内定者同士が早期に関係を築くきっかけとなります。同じ状況の仲間がいるという安心感は、入社までの孤独感を解消し、モチベーションを維持する上で大きな支えとなります。これらの内定者フォローは、単なる親睦を深めるだけでなく、ワークを通じてお互いの人となりを知り、入社後のスムーズなチームワークの土台を築くという目的も持っています。オンラインでの自己紹介リレーや共通の課題に取り組むイベントなど、内定者が受け身にならず、主体的に関われる工夫を凝らして取り組んでみましょう。
企業の良い面・悪い面も含めた情報提供を継続して行うこと
内定者が企業に求めているのは、耳障りの良いポジティブな情報だけではありません。むしろ、企業の抱える課題や仕事の厳しい側面といったネガティブな情報も含めて、包み隠さず伝えてくれる誠実な姿勢こそが、長期的な信頼関係を築く鍵となります。
例えば、社員との面談の場で「うちはこういう部分がまだ発展途上なんだ」「この仕事は正直、こういう大変さもある」といったリアルな情報を開示することで、内定者は「正直な会社だ」と感じ、入社後のギャップに対する覚悟と納得感を持つことができます。
入社前に役立つスキルアップ支援
「入社後、スムーズに業務に適応したい」「社会人として良いスタートを切りたい」という思いは、多くの内定者が共通して抱く願いです。このニーズに応えるのが、入社前に役立つスキルアップ支援です。ビジネスマナーや業界の基礎知識、業務で使うツールの使い方などを学べる内定者研修やe-ラーニングは、入社後の業務に対する漠然とした不安を具体的な自信へと変える効果があります。特にe-ラーニングは、場所や時間を選ばずに自分のペースで学習を進められるため、学業やプライベートと両立させたい内定者にとって満足度の高い内定者フォローです。ただし、重要なのは内定者の負担になりすぎない配慮です。あくまで任意参加とし、一方的に課題を詰め込むのではなく、内定者が「学びたい」と思えるような魅力的なコンテンツを提供しましょう。
「歓迎されている」と感じるパーソナルな連絡
数ある内定者フォロー事例の中でも、内定者の心に深く響くのは、一人ひとりに向けられたパーソナルなコミュニケーションです。一斉送信の事務連絡だけでなく、人事担当者が自分の名前や面接で話した内容を覚えていてくれた上で、「〇〇さんのこういう点に期待しています」といった個別のメッセージを送ることは、内定者に「自分は一人の人間として大切にされている」「歓迎されている」という強い実感を与えます。 細やかで温かみのあるコミュニケーションの積み重ねが、内定者と企業の心理的な距離を縮め、他社にはない特別なエンゲージメントを育みます。システム的なフォローだけでなく、人の温もりが感じられる対応こそが、最終的な入社の決め手になることも少なくありません。
【目的別】すぐに使える内定者フォローの具体事例20選
内定者フォローと一言でいっても、その目的は「内定者との関係構築」「企業理解の促進」「スキルの向上」「個別の不安解消」など多岐にわたります。目的を明確にしないまま手当たり次第に施策を行っても、期待する効果は得られません。大切なのは、自社がどの目的を重視し、それに合致した内定者フォローを計画的に実行することです。本章では、これら4つの目的に分類し、明日からでも企画・検討できる具体的な内定者フォロー事例を20個、厳選して具体的にご紹介します。
【関係構築】内定者同士・社員との交流を深める事例
事例1:内定者懇親会・食事会
内定者懇親会や食事会は、多くの企業が取り入れる王道の内定者フォロー事例です。リラックスした雰囲気の中で食事を共にすることで、内定者同士の連帯感が生まれ、入社前の不安を共有し、解消する場となります。また、現場の社員が参加すれば、会社のリアルな雰囲気を肌で感じてもらう絶好の機会にもなります。成功の鍵は、内定者が孤立しないような配席の工夫や、社員が積極的に話しかける雰囲気作りです。近年では、オンラインでの懇親会も増えており、クイズ大会や共通のテーマで話すブレイクアウトルームなどを活用して、遠方の内定者も参加しやすい環境を整える企業が増えています。
事例2:先輩社員との座談会・メンター制度
入社後の働く姿を具体的にイメージしてもらうためには、年齢の近い先輩社員との対話が非常に効果的です。少人数で行う座談会は、内定者が抱える素朴な疑問やキャリアへの不安を気軽に質問できる貴重な機会となります。さらに一歩進んだ内定者フォローとして、一人の内定者に一人の先輩社員がつく「メンター制度」を導入する企業も増えています。定期的な面談を通じて、内定期間中の学習の進捗相談からプライベートな悩みまで、一貫してサポートすることで、内定者は「自分を気にかけてくれる存在がいる」という強い安心感を得ることができます。
事例3:役員との交流会
会社のビジョンや未来の方向性を最も熱量を持って語れるのは、経営を担う役員です。役員との交流会を設けることは、内定者にとって「会社から大きな期待を寄せられている」という特別なメッセージとして伝わります。役員から直接、事業にかける想いや今後の展望を聞くことで、内定者は企業の将来性を確信し、入社意欲を大きく高めることができます。この内定者フォロー事例では、役員が一方的に話すだけでなく、内定者からの質問に真摯に答える時間を十分に確保することが重要です。会社のトップが自分たちと向き合ってくれる姿勢は、何よりの魅力付けとなり、内定者の心を掴みます。
事例4: グループワーク・チームビルディング研修
同期となる仲間とのチームワークを醸成することも、重要な内定者フォローの目的の一つです。共通の課題に取り組むグループワークや、ゲーム要素を取り入れたチームビルディング研修は、内定者同士の相互理解を深め、自然なコミュニケーションを促します。例えば、企業の理念や事業内容に関連したテーマでディスカッションやプレゼンテーションを行うことで、楽しみながら企業理解を深めることも可能です。このフォロー事例のポイントは、成果物の出来栄えを評価するのではなく、協力して課題解決に取り組むプロセスそのものを重視する姿勢を企業側が見せることです。
事例5:社内イベントへの招待(部活動、総会など)
企業の「素顔」を見せる最も効果的な方法の一つが、既存社員向けのイベントに内定者を招待することです。例えば、部活動の見学・体験会や、全社員が集まるキックオフミーティング(総会)、ボランティア活動などに参加してもらうことで、フォーマルな場では伝わらない社員同士の関係性やカルチャーを肌で感じてもらえます。この内定者フォロー事例は、内定者に「早くこの輪の中に入りたい」と思わせる効果が期待できます。ただし、内定者の学業などに配慮し、参加を強制しないこと、そして内定者が疎外感を感じないよう、社員が積極的にフォローする体制を整えておくことが不可欠です。
【企業理解】会社の魅力を伝え、入社後のイメージを掴んでもらう事例
事例6:オフィス・工場見学ツアー
自分がこれから働く場所の環境は、内定者にとって最大の関心事の一つです。オフィスや工場、店舗などを実際に見学してもらうツアーは、働くイメージを具体化させ、入社後のギャップを減らす効果的な内定者フォロー事例です。執務スペースだけでなく、社員食堂や休憩室といったリフレッシュスペースも見せることで、よりリアルな会社生活を想像できます。最近では、遠方の内定者向けに、社員がカメラを持って社内を案内する「オンラインオフィスツアー」を実施する企業も増えています。ただ見せるだけでなく、各部署で働く社員に仕事内容を紹介してもらうなど、双方向のコミュニケーションを組み込むと満足度がさらに高まります。
事例7:社内報・限定Webコンテンツの送付
内定期間中、定期的に会社の情報を届けることは、内定者の帰属意識を高める上で重要です。社員向けに発行している社内報を送付したり、内定者だけが閲覧できる限定Webサイトを開設したりする内定者フォローは、会社の「今」を伝え、関係性を維持するのに役立ちます。コンテンツとしては、新規プロジェクトの紹介、社員インタビュー、業界ニュースの解説などが考えられます。このフォロー事例のポイントは、事務的な連絡だけでなく、会社のカルチャーや人の魅力が伝わるような、読み物として楽しめるコンテンツを意識することです。
事例8:社員密着ドキュメンタリー動画の配信
テキストや写真だけでは伝わりきらない「人」の魅力を伝えるには、動画コンテンツが非常に有効です。様々な部署で働く先輩社員の1日に密着したドキュメンタリー動画を制作・配信する内定者フォロー事例は、仕事の具体的な流れから職場の人間関係まで、リアルな働き方を伝えることができます。営業職の社員が顧客と商談する様子や、エンジニアがチームで開発に取り組む風景などを見せることで、内定者は自分の将来の姿を重ね合わせやすくなります。プロが制作したような綺麗な動画でなくても、社員がスマートフォンで撮影した手作り感のある動画の方が、かえって親近感が湧き、好評な場合もあります。
事例9:内定者による採用パンフレットやサイト制作
内定者に「お客様」ではなく「仲間」として関わってもらうユニークな内定者フォロー事例が、次年度の採用ツール制作への参加です。内定者にプロジェクトチームを結成してもらい、学生目線で会社の魅力を伝える採用パンフレットやWebサイトの企画・制作を任せます。この取り組みを通じて、内定者は会社の事業や文化を深く理解しようと主体的に動くようになります。また、社員と協力しながら一つの目標に向かう経験は、強い当事者意識とエンゲージメントを育む絶好の機会となり、内定者自身の成長にも繋がります。
事例10:自社製品・サービスのプレゼント
自社の製品やサービスに愛着を持ってもらうことも、重要な内定者フォローの一つです。食品メーカーが自社製品の詰め合わせを送ったり、IT企業が自社開発のアプリやツールの無料利用権をプレゼントしたりする事例がこれにあたります。実際に製品を使ってもらい、その感想や改善提案などを求めることで、単なるプレゼントに留まらず、内定者を「未来の作り手」として扱うメッセージを伝えることができます。これにより、内定者は企業理解を深めると同時に、入社後、自分が関わる製品・サービスへの誇りと愛着を育むことができます。
【スキルアップ】入社後のスムーズな立ち上がりを支援する事例
事例11:内定者アルバイト・長期インターンシップ
入社後のミスマッチをなくし、即戦力化を促す上で最も効果的な内定者フォロー事例が、内定者アルバイトや長期インターンシップです。実際の業務に携わることで、仕事内容や社風への理解が飛躍的に深まり、入社前に実践的なスキルを身につけることができます。企業側にとっても、内定者の適性や能力を早期に把握できるメリットがあります。このフォローを実施する際は、学業への支障が出ないよう、勤務日数や時間に柔軟性を持たせることが絶対条件です。また、内定者を単なる労働力として扱うのではなく、明確な育成計画のもとで社員が指導にあたる体制を構築することが重要です。
事例12:eラーニングによる学習コンテンツ提供
内定者の「入社までに何か準備しておきたい」という学習意欲に応えるのが、eラーニングを用いた内定者フォローです。PCやスマートフォンでいつでもどこでも学べるため、学業や卒業旅行で忙しい内定者にとっても負担が少なく、人気の高い施策です。提供するコンテンツは、ビジネスマナーや情報セキュリティの基礎から、業界知識、プログラミングの初歩まで多岐にわたります。進捗状況をシステムで管理できるため、人事担当者が個々の学習状況を把握し、適切な声がけをすることも可能です。
事例13:資格取得の支援制度
業務に関連する専門資格の取得を支援することも、内定者のスキルアップとモチベーション向上に繋がる有効な内定者フォローです。例えば、IT企業が基本情報技術者試験の受験費用や参考書の購入費用を補助したり、不動産業界で宅地建物取引士の取得を奨励したりするケースが挙げられます。会社が費用を負担することで、内定者は金銭的な心配なく学習に集中できます。これは、個人の成長を積極的にサポートする企業文化であるという強力なメッセージとなり、内定者の学習意欲を効果的に引き出すことができます。
事例14:課題図書の提示と読書レポート
企業の理念や価値観、あるいはビジネスパーソンとしての基礎体力を養ってもらう目的で、課題図書を提示し、感想レポートの提出を求める内定者フォロー事例もあります。創业者の自伝や、業界の未来を論じた書籍などを通じて、企業のDNAや仕事への向き合い方を深く理解してもらうきっかけになります。このフォローのポイントは、単に読ませて終わりにするのではなく、提出されたレポートに対して人事担当者が丁寧にフィードバックを返すことです。さらに、内定者同士で読書会を開き、本の内容についてディスカッションする機会を設けることで、より深い学びに繋がります。
事例15:ビジネススキル研修
学生から社会人への意識転換を促し、入社後のスムーズなスタートを支援するために、集合型のビジネススキル研修を実施するのも定番の内定者フォローです。ロジカルシンキングやプレゼンテーション、タイムマネジメントといったポータブルスキルは、どんな職種でも役立つため、内定者の満足度も高い傾向にあります。近年ではオンラインでの研修も一般的になり、グループワークなどを取り入れることで、スキル習得と同時に内定者同士の交流を促進することも可能です。研修を通じて「社会人として成長できる環境がある」と感じてもらうことが、入社への期待感を高めます。
【個別ケア】一人ひとりの不安に寄り添う事例
事例16:人事担当者との定期的な1on1面談
内定者が抱える不安は一人ひとり異なります。その個別の不安に寄り添う上で最も有効なのが、人事担当者との定期的な1on1面談です。月に1回など頻度を決めて対話の機会を設けることで、内定期間中の些細な悩みや疑問をタイムリーに解消し、信頼関係を深めることができます。この内定者フォローでは、企業側が話すのではなく、内定者の話に耳を傾ける「傾聴」の姿勢が何よりも重要です。キャリアプランの相談からプライベートな悩みまで、安心して話せる「味方」がいるという感覚は、内定者にとって大きな心の支えとなります。
事例17:SNSやチャットツールでの気軽な相談窓口設置
電話やメールでは少し聞きにくい、ちょっとした疑問や相談事を気軽に投げかけてもらうための内定者フォロー事例として、LINEやSlackなどのチャットツールを活用した相談窓口の設置があります。内定者にとって普段から使い慣れたツールを用いることで、コミュニケーションの心理的なハードルを下げることができます。「〇〇の書類の書き方が分からない」「来週の懇親会の服装は?」といった小さな質問にも迅速に答えることで、内定者の不安を一つひとつ丁寧に取り除き、会社への親近感を醸成します。
事例18:内定者専用サイト・コミュニティの運営
内定者同士のコミュニケーションを活性化させ、帰属意識を高めるために、内定者専用のSNSやオンラインコミュニティを運営する内定者フォローも効果的です。自己紹介のスレッドを立てたり、内定者から社員への質問コーナーを設けたり、人事からの定期的な情報発信を行ったりすることで、内定期間中も常に会社や同期との繋がりを感じられる場となります。活発なコミュニティは、内定者同士が自然と悩みを相談し合い、励まし合う文化を育む土壌となり、企業が直接介入せずとも内定者の不安を和らげる効果が期待できます。
事例19:家族・保護者向けの説明会
特に新卒採用において、入社する企業に対する家族や保護者の理解と安心感は、内定者の意思決定に少なからず影響を与えます。そこで、保護者向けに事業内容や福利厚生、人材育成の方針などを説明する会を設ける内定者フォロー事例が増えています。これは「オヤカク(親確)」対策とも呼ばれます。会社のトップから直接、我が子を大切に育てるというメッセージを伝えることで、保護者の不安を払拭し、内定者を家族ぐるみで応援してもらう体制を築きます。誠実な対応は企業の信頼性を高め、間接的に内定辞退の防止に繋がります。
事例20:オファーメッセージの作成
内定通知(オファー)を出す際に、画一的な通知書だけでなく、パーソナライズされたメッセージを添えることは、内定者の心を掴む最初の重要な内定者フォローです。なぜあなたを採用したいのか、選考を通じて感じた魅力や期待している役割などを、採用に関わった面接官や役員の言葉で具体的に伝える「オファーメッセージ」を作成します。自分が個人として正当に評価され、強く求められているという実感は、内定者にとって何よりの喜びです。この特別なメッセージは、数ある内定先の中から自社を選んでもらうための、強力な最後の一押しとなります。
内定者フォローでよくある失敗・NG事例
上記で紹介した施策を行ったとしても、意図せず内定者の意欲を削ぎ、最悪の場合、内定辞退につながってしまうケースも少なくありません。熱心さのあまり過干渉になったり、逆に連絡が途絶えて不安にさせたりと、その失敗パターンは多岐にわたります。ここでは、多くの企業が陥りがちな内定者フォローのNG事例を具体的に解説します。自社の取り組みが、内定者にとって「ありがた迷惑」になっていないか、これらの失敗事例を他山の石として、ぜひ一度振り返ってみてください。
内定者任せにする放置フォロー
内定を出した後に連絡が途絶え、内定者を事実上放置してしまうのは、典型的な内定者フォローの失敗事例です。企業側は「学業の邪魔をしないように」という配慮のつもりでも、内定者からすれば「自分は本当に歓迎されているのだろうか」「忘れられているのではないか」という強い不安を抱く原因となります。特に、複数の内定を保持している学生は、手厚いフォローで継続的にコミュニケーションを取ってくれる企業に魅力を感じやすいものです。連絡が全くない「サイレント期間」が続くと、内定者の入社意欲は徐々に低下し、よりエンゲージメントの高い他社へ気持ちが傾いてしまうリスクが非常に高まります。内定承諾はゴールではなく、あくまでスタートライン。定期的な連絡を怠ることは、内定辞退の引き金を引く行為だと認識すべきです。
内定者への連絡や対応に差がある
内定者フォローにおいて、担当者が無意識のうちに特定の内定者とだけ親密になったり、逆にコミュニケーションが取りづらい内定者を避けたりと、対応に「差」が生まれてしまうことがあります。これは、組織としての公平性を欠き、内定者間に不信感を生む深刻なNG事例です。例えば、一部の内定者だけが参加する非公式な食事会を開いたり、特定の内定者にだけ頻繁に個別の連絡を取ったりする行為は、他の内定者に「自分は大切にされていない」という疎外感を与えます。また、優秀な内定者だけに手厚くフォローするような「えこひいき」が透けて見えると、チームワークを重んじる学生からは「不誠実な会社だ」と見なされかねません。内定者は、未来の同僚となる仲間たちです。全員に対して公平で誠実な対応を心がけることが、信頼関係の土台となります。
一方的で形式的なイベント
目的が曖昧なまま「とりあえず集めておこう」という発想で実施されるイベントは、内定者の時間を無駄にし、企業への期待を損なうだけの形式的なフォローに陥りがちです。例えば、内定式で何度も聞いた会社説明を繰り返したり、人事担当者だけが一方的に話し続ける懇親会を開催したりするケースがこれにあたります。内定者が本当に求めているのは、企業の宣伝文句ではなく、現場で働く社員のリアルな声や、同期となる仲間との双方向のコミュニケーションです。こうした内定者の本音を無視した一方的なイベントは、「この会社は自分たちのことを理解しようとしていない」という印象を与え、かえってエンゲージメントを低下させます。イベントを企画する際は、必ず「この会を通じて内定者に何を感じてほしいのか」という目的を明確にすることが不可欠です。
過度な課題や頻繁すぎる連絡
内定者の成長を願う熱意が空回りし、過干渉になってしまうのも、よくある内定者フォローの失敗事例です。入社への期待を高めるどころか、「監視されている」「自由がなさそう」といったプレッシャーや息苦しさを与えてしまいます。例えば、学業や卒業論文で多忙な時期にもかかわらず、大量の課題図書やレポートを課したり、毎日のように「今日の調子はどう?」とチャットで連絡したりする行為は、内定者の貴重な学生生活を侵害する過度な拘束と受け取られかねません。良かれと思ったサポートも、頻度や量が適切でなければ、内定者にとっては単なる負担でしかありません。内定者一人ひとりの状況や希望する連絡頻度を尊重し、「支援」と「干渉」の境界線を見極める冷静な視点が求められます。
ネガティブな情報(離職率など)を隠す
内定者に会社の悪いイメージを与えたくないという思いから、離職率や残業時間、過去の失敗談といったネガティブな情報を意図的に隠蔽する行為は、企業の信頼を根底から揺るがす最悪のNG事例です。現代では、口コミサイトやSNSを通じて、学生は企業に関するあらゆる情報を簡単に入手できます。その中で、企業側が不都合な事実を隠していることが発覚すれば、「不誠実な会社だ」というレッテルを貼られ、築き上げてきた信頼関係は一瞬で崩壊します。むしろ、課題や弱点を正直に開示した上で、「その課題を解決するために、今こんな取り組みをしている」と誠実に伝える方が、よほど内定者の信頼を得られます。企業の透明性は、内定者が安心して入社を決意するための重要な判断材料なのです。
内定承諾の強要や他社への辞退勧奨
いかなる理由があっても、内定者に対して内定承諾を強要したり、他社の選考を辞退するよう圧力をかけたりする行為は、断じて許されないコンプライアンス違反です。これは「オワハラ(就活終われハラスメント)」とも呼ばれ、学生に強い精神的苦痛を与えるだけでなく、企業の社会的信用を著しく失墜させます。具体的には、「今ここで承諾しないなら内定を取り消す」「他社の内定を辞退するよう今すぐ電話しなさい」といった言動が該当します。こうした威圧的な態度は、たとえその場で内定を承諾させたとしても、内定者の心に深い不信感を植え付け、入社後の早期離職や、SNSなどでの告発につながるリスクをはらんでいます。採用活動は、あくまで企業と学生が対等な立場で進めるべきであり、倫理観に基づいた誠実な対応が絶対条件です
内定者フォローを成功に導くための5つのポイント
NGポイントについて紹介いたしましたので、続いては効果的な内定者フォローを実施するための5つのポイントをご紹介いたします。内定者の心に響き、入社への期待感を着実に高めていくためには、一貫した方針に基づいたコミュニケーション設計が不可欠です。ここでは、数々の内定者フォロー事例から見えてきた、施策を成功に導くための普遍的な5つのポイントを解説します。
内定から入社まで、定期的かつ継続的に接点を持つ
内定者フォローを成功させる上で最も基本的なポイントは、内定承諾から入社日までの期間、定期的かつ継続的に接点を持ち続けることです。内定承諾直後は手厚く対応したものの、その後ぱったりと連絡が途絶えてしまう「内定承諾後の温度差」は、内定者に「自分は忘れられているのではないか」という強い不安を与え、内定辞退の大きな原因となります。理想的な連絡頻度は月に1回程度とされていますが、重要なのは頻度そのものよりも、常に「会社と繋がっている」という安心感を内定者に与え続けることです。懇親会などのイベントだけでなく、社内報の送付、Webコンテンツの更新通知、人事担当者からの気軽な季節の挨拶など、様々な手段を組み合わせて、内定者のエンゲージメントを維持していく姿勢が求められます。
オンラインとオフラインを目的別に使い分ける
現代の内定者フォローでは、オンラインとオフラインのそれぞれの長所を理解し、目的によって賢く使い分ける視点が不可欠です。例えば、ビジネスマナー研修やeラーニング、会社からの情報提供といった知識のインプットが目的の場合は、居住地を問わず参加しやすいオンラインが適しています。一方で、社員のリアルな熱量を感じてもらったり、内定者同士の偶発的な雑談から生まれる深い関係性を築いたりすることが目的であれば、オフラインの懇親会やオフィス見学が大きな効果を発揮します。どちらか一方に固執するのではなく、「この施策で達成したい目的は何か」を常に問いかけ、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッドなアプローチを考えることが、多様な内定者のニーズに応え、満足度を高める鍵となります。
一方的な情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを意識する
内定者フォローが失敗する典型的なパターンは、企業側が話したいことだけを伝える「一方的な情報提供」に終始してしまうことです。内定者は、何度も聞いた会社説明やビジョンよりも、社員のリアルな本音や、自分が抱えている些細な不安について対話したいと考えています。座談会や面談では、企業側が話す時間を最小限にし、内定者の質問や対話の時間を最大限に確保するよう心がけましょう。「何か質問はありますか?」と漠然と問うだけでなく、チャットツールなどで事前に質問を募集したり、匿名で質問できる仕組みを用意したりするのも有効です。内定者一人ひとりを「未来の仲間」として尊重し、その声に真摯に耳を傾ける双方向の姿勢こそが、信頼関係を築くための第一歩です。
「特別感」を演出し、歓迎している姿勢を伝える
数ある企業の中から自社を選んでくれた内定者に対し、「あなたはその他大勢の一人ではなく、私たちにとって特別な存在です」というメッセージを伝えることは、エンゲージメントを高める上で非常に効果的です。例えば、内定通知書に採用担当者や役員からの手書きのメッセージを添える、面接で話した内容を踏まえて「あなたの〇〇という経験に期待しています」と伝える、といったパーソナライズされたアプローチは、内定者の心に深く響きます。また、名前入りのウェルカムグッズを用意したり、誕生日にお祝いのメッセージを送ったりするのも良いでしょう。こうした少しの手間をかけた「特別感」の演出は、内定者に歓迎されている実感を与え、他社にはない強い繋がりを育むことに繋がります。
企業の情報をオープンにし、期待値を適切にコントロールする
入社後のギャップによる早期離職を防ぐためには、内定者フォローの段階で企業の情報をオープンにし、内定者の期待値を適切にコントロールすることが極めて重要です。会社の良い面や成功体験ばかりを強調するのではなく、現在抱えている課題や仕事の厳しい側面についても、誠実に伝える姿勢が求められます。誇大な表現で期待値を過度に上げてしまうと、入社後に「こんなはずではなかった」という失望感を生むだけです。むしろ、会社のリアルな姿を包み隠さず共有することで、内定者は納得感を持って入社を決意でき、困難なことがあっても乗り越えようという覚悟が生まれます。一時的な印象操作ではなく、長期的な信頼関係を築くための「正直さ」こそが、最終的に企業の利益となるのです。
内定者フォローに使えるおすすめツール・サービス紹介
効果的な内定者フォローを実施したくても、「担当者のリソースが足りない」「どんな施策が響くのかノウハウがない」といった課題を抱える企業は少なくありません。そうした悩みを解決し、人事担当者の負担を軽減しながらフォローの質を高めるのが、各種専門ツールやサービスです。コミュニケーションを円滑にするものから、入社前教育、イベント企画まで、その種類は多岐にわたります。ここでは、自社の目的や課題に合わせて最適な選択ができるよう、代表的な内定者フォローツールやサービスをカテゴリ別に分かりやすく紹介します。
LINEを活用したフォロー施策
今や学生の主要な連絡手段であるLINEは、内定者フォローにおいても非常に強力なツールとなります。メールよりも開封率が高く、プッシュ通知で確実に情報を届けられるため、連絡の見落としを防ぎます。多くの企業では、内定者向けのLINE公式アカウントを開設し、社内ニュースや社員紹介といった定期的な情報発信を行っています。また、チャット機能を使えば、内定者が抱える些細な疑問や不安を気軽に相談できる窓口となり、人事担当者との心理的な距離を縮めることができます。ただし、プライベートなツールであるため、連絡する時間帯に配慮したり、返信ルールのを明確にしたりするなど、適切な距離感を保った運用を心がけることが、信頼関係を損なわないための重要なポイントです。
採用一括かんりくん
「採用一括かんりくん」は、その名の通り採用活動全体を管理できるシステム(ATS)ですが、内定者フォローにおいても大きな力を発揮します。このツールの強みは、応募から選考、そして内定に至るまでの候補者情報を一元管理できる点にあります。これにより、面接で話した内容や個々の志向といったデータを踏まえた、一人ひとりに寄り添ったパーソナルなフォローが可能です。また、LINE連携機能も搭載しており、内定者への連絡をスムーズかつ確実に行うことができます。採用活動の効率化と、質の高い内定者フォローを両立させたい企業にとって、非常に心強いサービスと言えるでしょう。データに基づいた戦略的なフォローを実現したい場合に最適な選択肢です。
専用フォローツール「内定辞退防止くん」
「内定辞退防止くん」は、バヅクリ株式会社が運営するチームビルディングサービスです。このツールの最大の特徴は、ゲームやワークショップといった「遊び」の要素を取り入れた200種類以上の豊富なプログラムにあります。プロのファシリテーターがオンライン・オフラインでイベントを進行するため、企業側は企画や運営の負担なく、質の高い交流の場を提供できます。楽しみながら参加する中で、内定者は自然と素の自分をさらけ出し、同期との連帯感を深めたり、社員のリアルな人柄に触れたりすることができます。自社でのイベント企画がマンネリ化している、あるいは企画のノウハウがないといった課題を抱える企業にとって、まさに救世主となる内定者フォローサービスです。
学習・研修支援ツール(eラーニングなど)
入社後のスムーズなスタートを支援するために、内定期間中にスキルアップの機会を提供することも効果的な内定者フォローです。「School for Business」や「サイバックスUniv」に代表されるeラーニングサービスを活用すれば、ビジネスマナーやPCスキル、専門知識といった幅広い学習コンテンツを、時間や場所を問わず内定者に提供できます。「入社までに何か学んでおきたい」という意欲的な内定者のニーズに応えることで、学習機会の提供と入社後の即戦力化を同時に実現します。多くのサービスでは、学習の進捗状況を管理できるため、個々の状況に合わせた声がけやサポートも可能です。入社前教育に力を入れたい企業には必須のツールと言えるでしょう。
イベント型サービス(バヅクリ、TSUNAGなど)
「TSUNAG」のようなエンゲージメント向上を目的としたプラットフォームは、社内SNSのようなカジュアルなUIで、内定者同士や社員との継続的なコミュニケーションを促進します。こうしたサービスを活用することで、人事担当者は煩雑な業務から解放され、内定者一人ひとりと向き合うといった、より本質的な業務に集中することができるようになります。
まとめ:
効果的な内定者フォローの鍵は、画一的な施策の導入ではなく、自社の内定者や企業文化に合わせた「オーダーメイド」のプランニングにあります。そして、一度きりで終わらせず、内定者の反応を見ながら常に改善を続ける姿勢が不可欠です。
しかし、最も重要なのはツールや手法以前の意識改革に他なりません。内定者を「管理対象」ではなく「未来の仲間」として心から歓迎する。その真摯な姿勢が、あらゆる施策に血を通わせます。
「どうすれば内定者が嬉しいと感じるか」を考え抜き、ご紹介した施策をお試しいただけると幸いです。
「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。
私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。
人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。