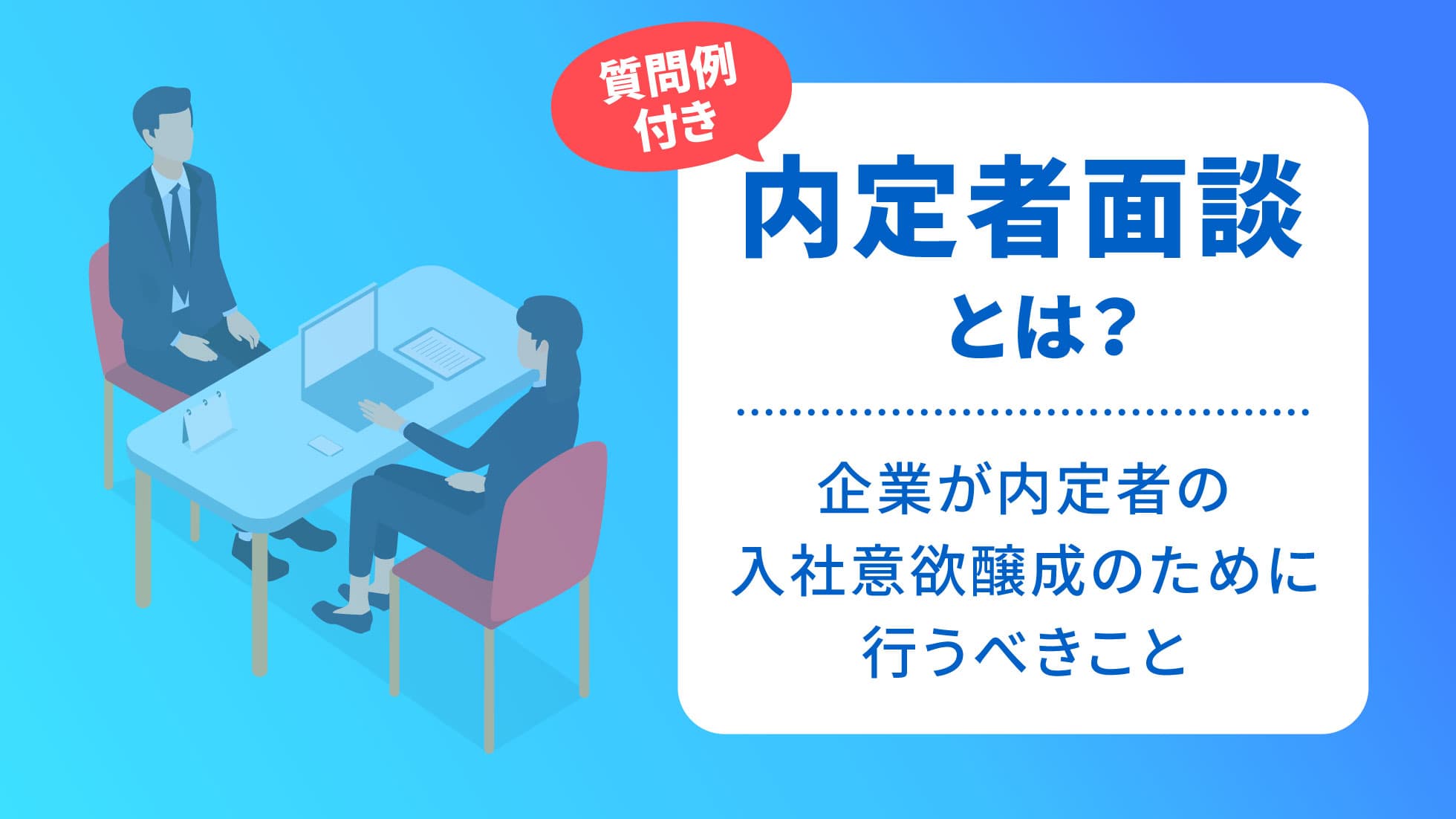内定辞退の増加に伴い、内定者フォローに力を入れる企業が増えてきています。本記事では内定者フォローの中でも比較的取り組みやすい内定者面談について、企業が取り入れる施策や準備について徹底解説します。
内定者面談とは?新卒採用で内定者面談を行う目的と重要性
内定者面談とは、企業が内定を出した応募者に対して行う面談であり、主に入社の意思確認や不安の解消を目的としています。一般的に、選考過程の「面接」とは異なり、企業側が一方的に評価する場ではなく、内定者との相互理解を深め、スムーズな入社へと導くための機会となります。
┗▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼
内定者フォロー完全ガイド:内定辞退を防ぐフォローの重要性と成功事例紹介
内定ブルー対策!大事な内定者を守るため企業がやるべきことは?
内定者面談を企業が実施する目的とは?
では、内定者面談を企業が実施する目的とは何でしょうか。内定者面談を実施する目的は大きく分けて3点あります。それぞれについて詳しく紹介します。
入社意思の確認
企業が内定を出した時点では、内定者はまだ他社の選考を受けることができ、最終的にどの企業へ入社するかを決定する自由があります。そのため、企業にとっては、内定者が本当に入社を決意しているのかを確認することが重要です。内定者面談を通じて、現在の状況や他社との比較検討の有無を把握し、必要に応じて企業の魅力を再確認する機会を提供します。
内定者の不安を解消する
多くの内定者は「本当にこの企業で良いのか」「入社後にうまくやっていけるか」といった不安を抱えています。特に、社会人経験のない新卒者にとっては、職場環境や業務内容が不透明であることが不安の大きな要因となります。内定者面談では、企業文化や働き方について詳しく説明し、職場の雰囲気を伝えることで、内定者の心理的な負担を軽減することができます。
労働条件・キャリアパスの認識を合わせる
給与や福利厚生、昇進の仕組みなど、労働条件に関する細かな部分を確認するのも内定者面談の重要な役割です。企業と内定者の間で条件に対する認識のズレがあると、入社後の早期離職につながる可能性があります。そのため、給与体系や昇進の流れ、将来的なキャリアパスについて明確に伝えることで、内定者が納得した上で入社を決意できるようサポートします。内定者面談は、単なる入社意思の確認にとどまらず、企業と内定者の関係を深める大切な場です。適切に実施することで、入社後のミスマッチを防ぎ、より良いスタートを切るための土台を築くことができます。
内定者面談を行うべきタイミングと頻度とは?
内定者面談は、適切な時期と頻度で面談を実施し、内定者が安心して入社を迎えられる環境を整えることが重要です。
内定者面談を実施する適切な時期
内定者面談を行うべきタイミングは、主に「内定承諾前」と「内定承諾後」の2つです。それぞれのタイミングが何故必要なのか具体的に紹介します。
まずは「 内定承諾前の面談(内定通知後〜内定承諾まで)」です。
この時期の面談は、内定者が入社を決断する前のフォローとして行われるケースが多く、特に「入社意思の確認」や「待遇の説明」を目的とします。内定者の迷いや懸念点を解消し、他社と比較検討している場合、自社をより魅力的に感じてもらうために必要となります。
続いて、「 内定承諾後の面談(内定承諾後〜入社まで)」です。
内定者が内定を承諾した後、特に内定式までの期間(6月〜9月)は、入社意欲が薄れやすい時期とされています。企業側のフォローが不足すると、内定辞退が発生する可能性があるため、不安の解消や入社後のビジョンを明確にし、選択に自信を持ってもらうことが重要です。
面談の頻度
内定者面談は、1回のみの実施にこだわる必要はありません。状況に応じて複数回実施することが効果的です。多く接触機会を設けられると、さらに内定承諾率は上がる可能性があります。内定承諾前に1回実施、内定承諾後に1回〜複数回実施するのが良いでしょう。
複数回の面談を通じて、内定者の不安を軽減し、入社後のミスマッチを防ぐことができます。また、上司や先輩社員との面談を組み合わせることで、職場への親近感を醸成し、入社意欲を高める効果も期待できるためです。
内定者面談を実施するための準備と流れ
本章では内定者面談を実施するための準備と流れについて、流れに沿ってご紹介します。
面談の内容・方向性の決定
まず初めに行うのは、面談の内要と方向性の決定です。内定者面談を成功させるためには、まず「面談の目的」を明確にすることが重要です。面談の主な目的として、入社意思の確認・内定者の不安解消・労働条件の説明・会社の魅力再確認などが挙げられます。
面談の方向性は、内定者の状況に応じて変える必要があります。例えば、入社を迷っている内定者には、不安を解消するための情報提供を重点的に行い、入社意欲の高い内定者には、会社のビジョンやキャリアパスについて深く説明することで、より前向きな気持ちで入社を迎えてもらえるでしょう。
また、1回の面談ですべてをカバーするのではなく、複数回に分けて実施することで、より丁寧なフォローが可能になります。面談の目的を明確にし、それに沿った質問リストや説明資料を準備しておくと、スムーズな進行が期待できます。
実施のタイミングと回数の決定
続いて行うのは、実施のタイミングと回数の決定です。内定者面談を実施する適切なタイミングは、先ほど紹介した「内定承諾前」と「内定承諾後」です。
一般的に、内定承諾後の6〜9月は内定辞退が増加する時期とされています。そのため、内定承諾後に定期的に面談を実施し、フォローアップすることが効果的です。また、内定式後(10月以降)にも面談を設定し、入社に向けた具体的な準備をサポートすることで、内定者の安心感を高められます。
担当の社員を決定
タイミングと回数が決定したら行うのは、担当の社員のアサインです。内定者面談の内容によって、適任の担当者を選ぶことが重要です。適切な担当者を配置することで、内定者の疑問に的確に答えられ、より深い信頼関係を築くことができます。
面談の目的や内容に応じて、適切な担当者を選定し、事前に役割を明確にしておくことで、内定者にとって有益な面談が実現できます。
内定者からの逆質問に備える
最後に内定者からの逆質問に備えておきましょう。面談では、企業側が質問するだけでなく、内定者からの逆質問に応えることも大切です。特に、内定者は「待遇面」や「キャリア形成」に関する具体的な情報を知りたがる傾向があるため、想定される質問をリストアップし、明確な回答を用意しておきましょう。想定質問への回答は、企業の魅力をアピールする機会でもあるため、ポジティブな情報を交えながら誠実に対応することが重要です。また、回答の一貫性を保つために、事前に面談担当者間で共有しておくと良いでしょう。
企業側が内定者面談で聞くべき質問リスト
内定者面談を実際に実行するとなった際には、より良い時間にするために何を聞けば良いのか迷う担当者様も多いのでは無いでしょうか。本章では内定者面談で聞くべき質問リストを紹介します。
入社意思の確認
内定者面談では、まず内定者が本当に入社する意思があるのかを確認することが重要です。特に、新卒採用の場合は他の企業と並行して選考を受けているケースも多いため、明確な意思を把握することが必要です。
「当社の内定を受諾する予定でしょうか?」と直接的に確認するのも有効ですが、より踏み込んだ質問をすることで、入社意欲の度合いを探ることができます。
- 「当社の内定を受けた際、どのようなことを考えましたか?」
- 「当社への入社を決める上で、他の企業と比較したポイントはありますか?」
- 「入社するにあたって、最後に確認しておきたいことはありますか?」
また、もし入社に対する迷いが見られる場合は、その理由をヒアリングし、不安を解消するための情報を提供しましょう。例えば、社風や職場環境に対する不安がある場合は、社員の体験談やオフィス見学を提案するのも有効です。
就職活動の継続状況
内定者が就職活動を継続しているかどうかを把握することも、企業側にとって重要なポイントです。内定者が他社と比較検討している場合、適切なフォローを行わないと内定辞退につながる可能性があるため、慎重にヒアリングを行いましょう。
- 「現在、他の企業の選考を受けていますか?」
- 「就職活動はいつまで続ける予定ですか?」
- 「当社と他社のどの点で迷っていますか?」
- 「最終的な決断はいつ頃を予定していますか?」
無理に選考状況を詮索するのではなく、内定者が何に不安を感じているのかを聞き出し、適切なフォローをすることが大切です。 例えば、他社と比較して待遇面に不安がある場合は、福利厚生やキャリアパスについて詳細に説明し、安心感を与えることができます。
会社・業務に対する不安や疑問
内定者の多くは、入社後の仕事内容や職場の雰囲気について具体的なイメージを持ち切れていません。そのため、業務内容に対する疑問や不安をヒアリングし、解消することが重要です。
- 「入社後の仕事内容について、どのようなイメージを持っていますか?」
- 「業務に関して不安に感じていることはありますか?」
- 「職場の雰囲気や文化について気になる点はありますか?」
- 「仕事を通じてどのようなスキルを身につけたいですか?」
また、職場環境や働き方に関する情報も、内定者が安心して入社を決めるための重要な要素です。可能であれば、配属先の先輩社員と交流できる機会を設けることで、よりリアルなイメージを持ってもらうことができます。
労働条件・配属に関する懸念点
労働条件や配属先に関する誤解があると、入社後の早期離職につながる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
- 「労働条件について、不安な点はありますか?」
- 「給与や福利厚生について、確認しておきたいことはありますか?」
- 「配属先の希望があれば教えてください。」
- 「キャリアパスについて気になることはありますか?」
特に、新卒採用では**「配属先が決まっていないことに対する不安」**が多い傾向にあります。その場合、過去の配属実績や決定プロセスについて説明し、不安を軽減できるよう努めましょう。
また、労働条件の説明は慎重に行う必要があります。給与や賞与、福利厚生についての詳細を明確に伝え、誤解が生じないようにすることが大切です。 説明が曖昧だと、入社後のギャップを生み、早期退職のリスクを高める可能性があります。
内定者面談のよくある逆質問とは?
先ほど、面談では、企業側が質問するだけでなく、内定者からの逆質問に応えることも大切ですとお伝えしました。内定者からの逆質問は多くが想定しておくことで、どの担当者が面談を行っても同じ対応をすることができます。
具体的にどのような質問が多いのか、良くある逆質問をご紹介します。
給与や賞与、有給休暇などの福利厚生や待遇について教えてください
給与や賞与、有給休暇などの待遇面は、内定者にとって特に関心が高いポイントです。内定者面談では、初任給や賞与の支給タイミング、昇給制度、有給休暇の取得率や運用ルールなどについて具体的に伝えることが重要です。
例えば、**「初任給は〇〇円で、賞与は年〇回支給されます」と具体的な数字を提示することで、内定者が将来の生活設計をイメージしやすくなります。また、有給休暇についても、「取得率は〇〇%で、繁忙期を除けば比較的取得しやすい環境です」**など、実際の運用ルールを含めて説明することで、内定者の不安を解消できます。
さらに、**「入社〇年目で年収〇万円に昇給した社員がいます」**などの実例を交えると、キャリアアップのイメージがしやすくなります。有給休暇の取得についても、実際の取得事例を紹介し、働きやすい環境であることを伝えましょう。
新人研修の内容が知りたいです
内定者が研修内容を質問する背景には、**「入社後にきちんと仕事を覚えられるのか」「未経験でも活躍できるのか」**といった不安があります。そのため、研修の流れを明確に伝え、安心感を持ってもらうことが大切です。
具体的には、**「入社後〇ヶ月間は基礎研修があり、その後OJT研修を通じて業務を習得していきます」と説明することで、学習プロセスが明確になります。また、「ビジネスマナー研修や実務に直結する研修も実施し、段階的にスキルを身につけることができます」**といった詳細を加えることで、より具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。
また、研修後のフォローアップについても、**「定期的にメンターや先輩社員との面談を行い、相談できる環境を整えています」**と伝えることで、サポート体制の充実をアピールできます。
配属先は決定していますか
配属先に関する質問は、**「自分に合った環境で働けるのか」「希望する業務を担当できるのか」**といった内定者の不安を反映しています。
もし配属先がすでに決定している場合は、**「〇〇部署に配属予定で、主な業務内容は〇〇です」と明確に伝えましょう。その際、「チームの雰囲気は〇〇で、先輩社員がしっかりフォローします」**と付け加えることで、職場環境のイメージを持ちやすくなります。
配属先が未確定の場合は、**「入社後の研修期間を経て適性を判断し、〇月頃に正式決定します」と説明し、配属決定までのプロセスを明確に伝えましょう。また、「過去の配属実績として〇〇部門に〇%の内定者が配属されています」**と具体的なデータを示すことで、安心感を与えることができます。
若手社員のキャリアパスを教えてください
内定者は、自身のキャリアプランを具体的に描くために、企業内での成長機会や昇進の流れを知りたいと考えています。そのため、**「一般的なキャリアパス」と「個人の希望に応じたキャリア形成の柔軟性」**を併せて説明するとよいでしょう。
例えば、**「入社3年目でリーダー職に昇格し、その後マネージャーや専門職に進むキャリアがあります」と、具体的な昇進例を挙げると、将来のイメージが明確になります。さらに、「本人の希望や適性に応じて、他部署への異動や海外勤務のチャンスもあります」**といった柔軟なキャリアパスを示すことで、より魅力的に伝えられます。
また、**「〇年目でこういうスキルを習得する」「〇年後にはこんな業務を担当する」**といった具体例を交えることで、入社後の成長ビジョンが明確になります。実際にキャリアアップを果たした社員の事例を紹介するのも効果的です。
入社までに準備するべきことはありますか
この質問をする内定者は、入社前に何をすべきかを把握し、スムーズなスタートを切りたいと考えています。そのため、「必須の準備」と「推奨される準備」の2つに分けて説明するとわかりやすいでしょう。
必須の準備としては、**「入社前に必要な書類の提出」や「健康診断の受診」などを挙げ、期限を明確に伝えます。一方、推奨される準備としては、「業務に役立つスキルや資格の学習」「事前に読んでおくとよい書籍」**などを紹介すると、前向きに取り組んでもらいやすくなります。
例えば、**「プログラミングの基礎を学んでおくと、業務の理解がスムーズになります」や、「この業界の動向を知るために〇〇という書籍を読んでおくと良いでしょう」**といったアドバイスを加えることで、内定者が具体的な行動を起こしやすくなります。
また、入社前の不安を軽減するために、**「同期との交流の場として、内定者向けの懇親会を実施予定です」**などの情報を提供するのも有効です。
内定者面談で企業が避けるべきNG行動と成功させるためのポイント
面談の日程を早めに確定する
内定者面談の日程を早めに決定し、スムーズに調整することは非常に重要です。内定者にとって、面談は入社の意思を固めるための大切な機会であり、適切なタイミングで実施することで、内定辞退のリスクを軽減できます。
面談は内定通知後1〜2週間以内に設定するのが理想的です。時間が空きすぎると、内定者が他社の選考を進める可能性が高まり、入社意思が揺らぐこともあります。特に、新卒採用の場合は複数の企業と比較検討していることが多いため、早めの面談でフォローを行うことが重要です。
また、内定者の都合に配慮し、柔軟な日程調整を行うこともポイントです。対面面談にこだわらず、オンライン面談や電話面談などの選択肢を用意することで、内定者が気軽に参加しやすくなります。 企業側から候補日時を複数提示し、内定者に選んでもらう形を取ると、スムーズな調整が可能になります。
他社を批判して自社を持ち上げる
内定者面談では、自社の魅力を伝えることが重要ですが、他社を批判することで相対的に自社の評価を高めようとするのは逆効果です。他社の悪い点を指摘すると、内定者は「この会社は競合を悪く言う文化があるのかもしれない」「他社を否定しなければ自社の魅力を伝えられないのか」と感じ、企業への不信感を抱く可能性があります。
代わりに、自社の強みや特徴を前向きに伝えることを意識しましょう。例えば、「当社は〇〇の制度が充実しており、若手の成長をサポートする環境が整っています」など、自社の良さを具体的なデータや事例を交えて説明すると、内定者に魅力が伝わりやすくなります。また、他社を引き合いに出す場合でも、「〇〇業界ではこのような特徴がありますが、当社ではこうした取り組みを行っています」と、中立的な視点を持つことが大切です。
早期の内定承諾を強要する
内定者がじっくりと考えたうえで納得して入社を決断できるようにすることが重要です。企業が強引に「〇月〇日までに返事をください」とプレッシャーをかけたり、「今すぐ決めないとこのチャンスを逃しますよ」と煽るような発言をしたりすると、内定者は不安を感じ、かえって辞退のリスクが高まります。
特に新卒採用では、内定者はまだ他社の選考が進行中であることが多く、企業の比較を行っている最中です。この段階で強引な意思決定を迫ると、「本当にこの企業で大丈夫なのか?」と疑念を抱かせる要因になってしまいます。
企業としては、内定者が安心して決断できる環境を整えることが大切です。例えば、「迷っていることがあれば相談してください」「必要であれば追加で情報提供します」といったサポートの姿勢を見せることで、内定者との信頼関係を築くことができます。また、**「承諾期限までに不安があれば個別面談を実施します」**などのフォロー体制を整えることも効果的です。
曖昧な回答や誤解を招く説明
内定者面談では、給与・待遇・昇給制度・配属先・キャリアパスなどについて質問されることが多くあります。企業としては、できる限り具体的かつ正確な情報を伝え、曖昧な回答を避けることが重要です。
例えば、以下のような回答は避けるべきです。
「給与は〇年目には〇〇万円くらいになりますよ(実際には例外的なケース)」
「残業はほぼありません(実際には時期によって繁忙差がある)」
「研修制度はしっかりしています(内容を具体的に説明しない)」
このように、不正確な情報を伝えてしまうと、入社後のギャップにつながり、早期離職のリスクが高まります。企業側としては、具体的なデータや事例を交えながら、リアルな情報を提供することが大切です。
例えば、
「平均残業時間は〇時間で、繁忙期には〇時間になることがあります」
「昇給は年〇回あり、実績に応じて〇万円の昇給が可能です」
「研修では〇〇のプログラムを用意し、〇ヶ月間のOJTを実施しています」
といった形で、数値や具体例を交えて伝えることで、内定者に正確な情報を提供し、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
内定者が話しやすい雰囲気をつくる
内定者面談では、選考時の面接とは異なり、できるだけリラックスした雰囲気をつくることが大切です。内定者が安心して本音を話せる環境を整えることで、不安や疑問を率直に伝えてもらいやすくなります。
具体的には、形式ばった面談ではなく、カジュアルな対話を意識することが重要です。 例えば、最初にアイスブレイクを取り入れ、「最近どんなことに興味がありますか?」といった軽い話題を振ることで、緊張をほぐすことができます。
また、企業側の担当者が過度にフォーマルな態度を取ると、内定者は「評価されているのではないか」と感じ、遠慮して本音を話しにくくなります。そのため、適度にフレンドリーな会話を交えながら、内定者が自然に話せる空気を作ることが大切です。
さらに、**「あなたの考えを聞かせてください」「気になっていることは何でも聞いてくださいね」**といった促しを入れることで、内定者が積極的に質問しやすくなります。面談を一方的な説明の場にせず、双方向のコミュニケーションを意識することで、内定者との信頼関係を深めることができます。
内定者の不安を積極的に解消する
内定者の多くは、入社前にさまざまな不安を抱えています。**「本当にこの会社でいいのか」「業務についていけるか」「職場の雰囲気に馴染めるか」**といった疑問を持つのは自然なことです。企業側がこれらの不安を適切に解消することで、内定者の入社意欲を高めることができます。
内定者の不安を解消するためには、以下のような対応が有効です。
業務内容や配属先について具体的に説明する
内定者は、自分の担当する仕事について明確なイメージを持っていないことが多いため、できるだけ具体的に業務内容を説明しましょう。配属が未定の場合でも、**「過去の配属実績」や「配属決定のプロセス」**を伝えることで、安心感を持たせることができます。
入社後のサポート体制を説明する
**「研修制度」「メンター制度」「フォローアップ面談」**など、入社後の支援体制を詳しく伝えることで、内定者の不安を軽減できます。特に新卒の場合、社会人経験がないため、入社後にどのように成長できるのかを明確にすることが重要です。
現場社員との交流機会を設ける
先輩社員との座談会や懇親会を通じて、実際の職場環境を知ることができれば、入社後のイメージが湧きやすくなります。内定者がリアルな声を聞くことで、「この会社なら安心して働けそう」と感じてもらうことができます。
疑問や不安をヒアリングし、丁寧に回答する
「何か不安なことはありますか?」と聞くだけではなく、具体的な質問を投げかけることで、内定者が本音を話しやすくなります。例えば、**「会社の制度や業務内容について、もっと詳しく知りたいことはありますか?」**と聞くことで、内定者の関心や不安を引き出しやすくなります。
企業が内定者の入社意欲醸成のために行うべきこと
内定者の状態を把握する
内定者の入社意欲を高めるためには、まず彼らの状態を正確に把握することが重要です。多くの企業で見落とされがちなのは、内定者が何を不安に感じ、どのような期待を抱いているのかを把握できていない点です。特に、「キャッチアップ不足」は内定辞退の大きな要因となっており、企業側の適切なフォローが求められます。
効果的な状態把握の方法としては、アンケートの実施や定期的なヒアリングが挙げられます。例えば、内定者に対して以下のような情報を収集することで、適切なサポートを提供できます。
・入社意欲の変動(志望度の変化がないか)
・業務理解度(職種や仕事内容に対する理解がどの程度あるか)
・・懸念点や不安(社風・配属先・キャリアパスなどについての不安はないか)
こうした情報をもとに、内定者ごとにフォロー内容を調整することで、効果的なコミュニケーションが可能になります。
注視するべき内定者を見極めて見守る手立てを取る
内定者全員を一律に対応するのではなく、特に注意が必要な内定者を見極め、適切にフォローすることが重要です。例えば、以下のような内定者は、特に慎重な対応が求められます。
・他社の選考を継続している内定者
・業務や待遇面で不安を抱えている内定者
・企業とのコミュニケーションが希薄な内定者
こうした内定者を見極めるために、**「フラグ管理」や「アラート機能」**を活用すると効果的です。例えば、内定者のアンケート結果をもとに、特定の条件に該当する内定者にフラグを付与し、重点的にフォローを行う仕組みを導入することで、辞退リスクの高い内定者に先回りして対応できます。
また、定期的なチェックポイントを設け、面談やオンラインミーティングを通じてフォローを行うことで、内定者が抱える不安を早期に解消し、入社への意欲を維持しやすくなります。
必要な情報を適切なタイミングで豊富に提供する
内定者の入社意欲を醸成するためには、必要な情報を適切なタイミングで提供することが不可欠です。特に、以下のような情報は、入社前の不安を解消するうえで重要な役割を果たします。
・企業のビジョンや文化(企業理念、職場の雰囲気、働き方の特徴)
・業務内容の詳細(具体的な仕事内容、1日の業務フロー、研修内容)
・キャリアパスや成長機会(昇進の仕組み、評価制度、スキルアップの支援)
・社内イベントや交流の機会(懇親会、内定者向けの研修、先輩社員との交流会)
これらの情報は、一度にまとめて伝えるのではなく、段階的に提供することが効果的です。例えば、内定承諾直後は会社のビジョンや文化を伝え、入社が近づくにつれて業務内容や具体的な働き方を説明するなど、タイミングを工夫することで、内定者の興味を引き続けることができます。
企業の発信した情報を確実に内定者に確認してもらえるようにする
情報を提供しても、内定者が確実に受け取り、理解しているかどうかを確認することも重要です。従来のメールや電話では、内定者が情報を見逃したり、確認するタイミングが遅れたりするケースが多くあります。
そこで有効なのが、**LINEを活用した採用管理システム「採用一括かんりくん」**です。LINEは内定者の目に留まりやすく、プッシュ通知機能を活用することで、情報の受信率を高めることができます。
「採用一括かんりくん」×LINEの活用メリット
・プッシュ通知で重要な情報を確実に届ける
・リッチメニューを活用し、必要な情報に簡単にアクセスできる
・シナリオ配信機能で、適切なタイミングで情報を自動送信
・アンケート機能を活用し、情報が適切に伝わっているかをチェック
例えば、**「入社までに準備しておくこと」**に関するリマインドメッセージをLINEで自動送信し、内定者がチェック済みかどうかを確認することも可能です。これにより、内定者が確実に情報を受け取り、スムーズな入社準備を進めることができます。
┗ LINE搭載の採用管理システム「採用一括かんりくん」で解決→資料ダウンロード
まとめ
内定者の入社意欲を高めるためには、以下のポイントを意識したフォローが必要です。
・内定者の状態を把握し、不安や期待を正確に理解する
・辞退リスクの高い内定者を見極め、重点的にフォローを行う
・業務内容や社風、キャリアパスなどの情報を適切なタイミングで提供する
・LINEを活用して情報を確実に届け、受信状況を把握する
「採用一括かんりくん」を活用することで、工数をかけずに効果的なフォローを実施し、内定者のエンゲージメントを高めることが可能になります。
内定辞退を防ぎ、優秀な人材を確実に確保するためにも、入社までのフォロー体制を整え、内定者との関係を強化することが重要です。
「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。
私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。
人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。