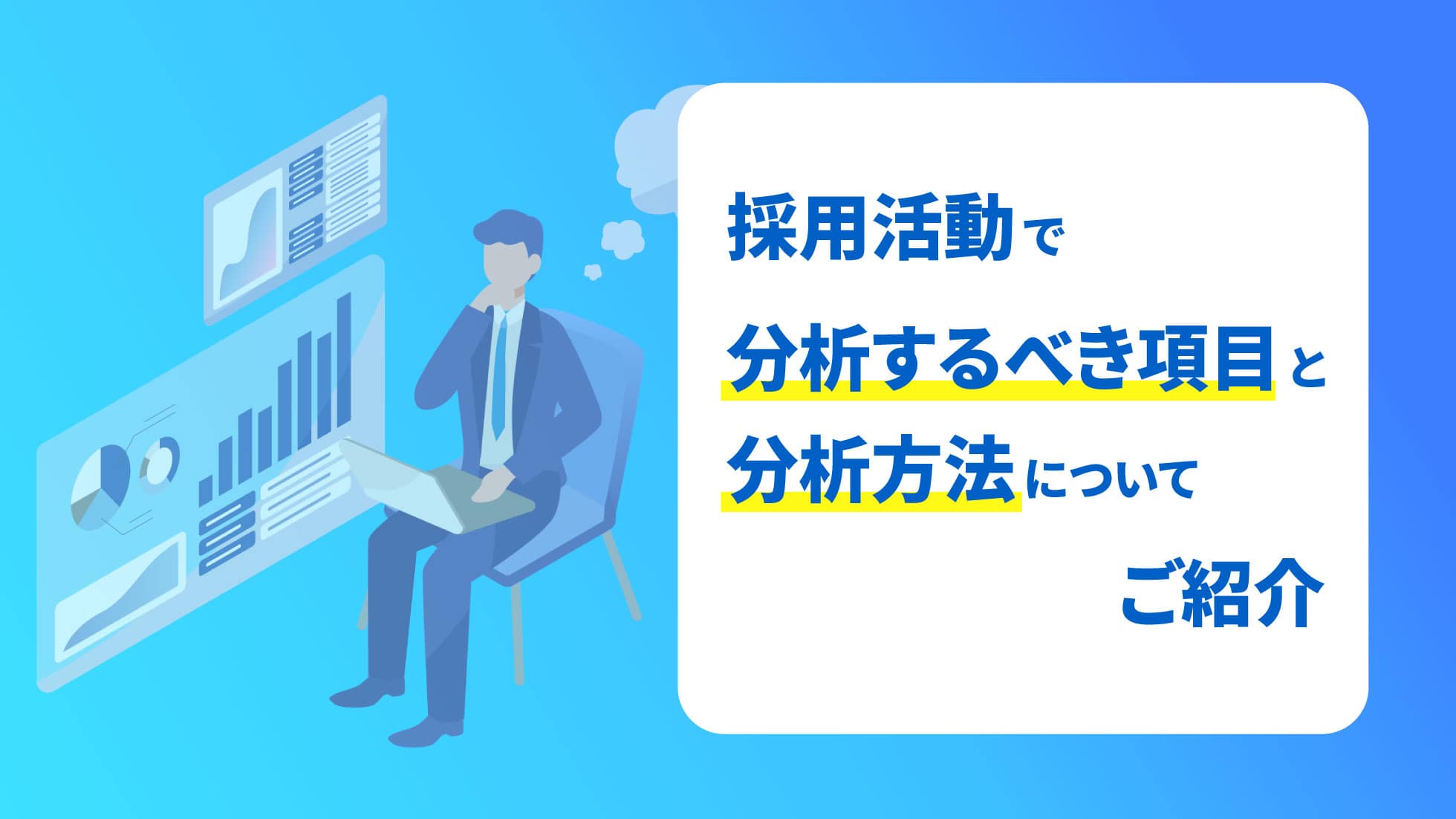「採用戦略アップデートのためのデータ分析」レポート
採用活動において分析を行うことは重要ですが、どのような項目を分析すれば良いのかやどのように分析をすれば良いのかが分からないということもあるのではないでしょうか?
本記事では、採用活動で分析するべき項目と分析方法について紹介しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
採用活動での分析の必要性
採用活動において分析は、自社の課題を適切に把握することや次年度以降の採用活動をより良くしていくために必要です。
ナビ媒体やエージェント、イベントなど様々な応募経路を利用している場合は、それぞれの応募経路ごとの応募者数や採用数を確認することで、より自社にマッチした応募経路を見つけることができます。応募者数や採用数が多いサービスを見つけることができれば、予算配分を適切にすることができ、コストの最適化を行うことができます。
分析というと定量的な部分だけを確認しがちですが、候補者と面接官との相性や候補者一人一人に合わせた魅力づけができているかなどの定性的な部分も合わせて確認することが重要です。
採用活動で分析・収集するべきデータとは

採用活動を効率的かつ効果的に行うためには、データを収集・分析し、課題を明確化することが重要です。採用の各プロセスで得られるデータを適切に活用することで、採用単価の削減や内定辞退率の低減につながります。以下では、採用活動で収集するべきデータを4つのカテゴリに分けて紹介します。
人数に関するデータ
1つ目に収集するべきデータは、人数に関するデータです。以下のデータを収集・分析することで、母集団形成の効率や選考プロセスの課題が明確になります。
- 応募者数全体:自社の求人に対する応募者の総数。
- 媒体別応募者数:各求人媒体ごとの応募者数。
- 説明会参加者数:合同説明会や個別説明会への参加者数。
- 選考通過者数・辞退者数:各選考プロセスごとのデータを把握することで、どの段階で辞退が多いのか分析可能。
- 内定者数・入社者数:内定承諾率や実際の入社率を測定する指標として重要。
コストに関するデータ
2つ目に収集するべきデータは、コストに関するデータです。採用活動では、経済的なコストの把握も欠かせません。以下の項目を収集し、採用コストにおける収支の全体像を明らかにします。
- 媒体ごとの広告費用:各媒体への出稿費用と応募者数を比較し、費用対効果を分析。
- 採用イベントの開催費用:説明会や懇親会などの開催にかかるコスト。
- 採用1人あたりの単価:採用にかかった総費用を採用人数で割った数値。
- 人件費:採用担当者や面接官の活動にかかった時間を時給換算し算出。
時間に関するデータ
3つ目に収集するべきデータは、時間に関するデータです。採用活動では、計画を立てる段階から入社に至るまで、多くの時間を要しています。採用活動にかけている時間を把握することで、業務の効率化を図ることもできます。以下の項目を収集しましょう。
- 採用全体の期間:母集団形成から内定、入社までにかかった日数。
- 選考プロセスごとの期間:各ステップ間に要した日数を明確にし、ボトルネックを特定。
- 採用業務にかかる時間:説明会準備や面接の時間を測定し、効率改善を検討。
施策に関するデータ
最後に収集するべきデータは、施策に関するデータです。採用活動の中で実施した具体的な施策に関するデータも、今後継続するのか、改善するのか、データを基に振り返りをすることが重要です。以下を収集し、施策の効果を検証します。
- 媒体で利用したキャンペーンやイベント施策の効果:特定の広告やプロモーションによる応募者数や通過者数の増加を測定。
- フォロー施策の結果:内定者フォローやリマインド施策が辞退率に与えた影響を分析。
- 選考方法の変更結果:新たに導入した面接形式や適性検査の結果を比較・検証。
採用における分析の基本原則

前章で紹介した採用データを収集したら、いよいよ分析を行います。採用における分析では、以下の基本原則を押さえることで、採用活動全体を正確に評価し、具体的な改善ポイントを見つけることができます。
1:目標との乖離を確認する
1つ目の原則は、「目標との乖離を確認する」ことです。分析を始める際は、まず目標との乖離をざっくり把握することが重要です。たとえば、採用人数やコスト目標に対してどれだけの差異があるのかを確認します。
最初に全体的な状況を確認することで、分析の方向性を明確にできます。特に、媒体単位やキャンペーン単位といった大枠の数値を見ることで、大まかな傾向や課題のある領域を見つけ出せます。細かい分析に入る前に全体像をつかみ、本質的な課題を効率よく特定しましょう。
2:比較する
2つ目の原則は、「比較する」ことです。集計したデータを「比較」することで、新たな知見を得ることができます。比較には、以下のような方法があります:
- 前年と当年の比較
- 新卒採用と中途採用の比較
- 採用手法や媒体ごとの比較
例えば、新卒採用と中途採用のコストを比較することで、どの採用方法がより費用対効果が高いのかが明らかになります。
3:時系列でみる
3つ目の原則は、「時系列でみる」ことです。データの時間軸を意識することで、時系列での傾向やパターンを把握しやすくなり、未来の予測や戦略の策定に役立ちます。
たとえば、以下のような時系列データを分析することで、変化の原因を探ることができます:
- 数年間にわたる応募者数や内定者数の推移
- 採用時期ごとの媒体効果の違い
- 早期離職者数の増減
時系列での分析は、季節性やトレンドの理解に役立ち、特定の時期に集中すべき施策を明確にします。
4:要因分解する
最後に紹介する原則は、「要因分解をする」ことです。データから見える傾向や課題に対して、その「要因」を分解して探ることが重要です。たとえば、応募者数が減少している場合には、以下の切り口で要因を特定します:
- 媒体別の応募者数の差異
- 説明会やイベントの集客効果
- 求人内容やターゲット層のミスマッチ
要因を具体的に分解することで、どの部分にリソースを集中すべきかを明確にできます。例えば、ある媒体で応募者数が極端に少ない場合、その媒体の利用を見直すか、別の手法にリソースを振り分ける判断が可能です。
採用活動において分析するべき項目
上記で順に説明してきたように、まずはデータを収集し、具体的なデータをもとに各プロセスを分析することが重要です。本章では、採用活動で注目すべき3つの指標とその算出方法について解説します。
費用対効果
採用活動の費用対効果を分析することで、予算の最適化や効率的な採用チャネルの選定が可能になります。費用対効果を測定するためには、以下のデータを収集します:
- 採用コスト
- 外部コスト:求人広告費、採用イベント費用、人材紹介会社への支払いなど。
- 内部コスト:採用担当者や面接官の人件費、求職者の交通費、内定者懇親会費用など。 - 採用成果
- 採用人数、内定者数、入社者数など。
算出の仕方
算出式は以下の通りです:
費用対効果 = 採用成果 ÷ 採用コスト
この指標を用いることで、費用に対してどれだけの成果を上げられているかを把握できます。また、求人媒体ごとのコストパフォーマンスを比較することで、無駄なコストの削減につながります。
歩留まり率
歩留まり率は、採用プロセスにおける各選考ステージでの通過者数の割合を示します。このデータを分析することで、選考プロセスのどの段階に課題があるのかを特定できます。
算出の仕方
歩留まり率は以下の式で算出します:
歩留まり率 =(選考を通過した人数 ÷ 選考に進んだ人数)× 100
たとえば、応募者100名のうち一次選考を通過した人数が30名の場合、
30 ÷ 100 × 100 = 30%
一次選考の歩留まり率は30%となります。
各選考ステージの歩留まり率を比較することで、応募者の離脱が多いプロセスを特定できます。その結果、採用プロセスの改善に向けた具体的な施策を立案可能です。
エンゲージメント
候補者や内定者とのエンゲージメントを測ることで、選考辞退率や内定辞退率を低減し、採用活動の成果を向上させることができます。
算出の仕方
エンゲージメントは以下の指標を用いて評価します:
- メールやLINEなどの連絡に対する応答率
- 面接や説明会への参加率
- 内定者フォローへの反応率
たとえば、内定者20名のうち懇親会に参加した人数が16名の場合、
16 ÷ 20 × 100 = 80%
内定者懇親会の参加率は80%となります。
エンゲージメントを数値化し、コミュニケーションやフォロー体制を見直すことで、候補者との信頼関係を強化できます。
目的別データ分析例
採用活動を改善し、より効率的なプロセスを実現するためには、目的別にデータを分析し課題を特定することが重要です。以下では、費用対効果の高い求人媒体の把握、選考辞退の削減、内定辞退の削減に焦点を当てたデータ分析例を解説します。
1:費用対効果の高い求人媒体を把握する
採用活動において、多額のコストが発生する求人媒体の選定は、費用対効果を分析することで最適化できます。
分析手法
求人媒体ごとのコストと採用人数を基に、以下の計算式を使用します:
費用対効果 = 求人媒体にかかった費用 ÷ 求人媒体経由で採用された人数
例
- 媒体A:費用100万円 ÷ 採用人数2名 = 1名あたり50万円
- 媒体B:費用160万円 ÷ 採用人数4名 = 1名あたり40万円
この例では、媒体Bの方が費用対効果が高いことがわかります。費用対効果が低い媒体に対しては掲載を見直し、効果の高い媒体に投資を集中させることで、コスト削減と採用効率の向上が期待できます。
2:選考辞退を減らしたい
選考辞退が多い場合は、各工程の歩留まり率を分析して、課題のある要因を特定します。
分析手法
歩留まり率を以下の計算式で算出します:
歩留まり率 = 次の工程に進んだ人数 ÷ 前工程の人数 × 100
例
一次面接の受験者が100人で、そのうち二次面接に進んだのが40人の場合:
40 ÷ 100 × 100 = 歩留まり率40%
歩留まり率が低い場合は、以下の要因を仮説として検討します:
- 候補者に負担がかかっていないか
- プロセスに時間がかかっていないか
- 用意しているコンテンツの内容は魅力的か
- 用意している評価は適切か
改善策として、選考プロセスの迅速化や候補者とのコミュニケーションの見直しはすぐに変更が可能です。
3:内定辞退を減らしたい
内定辞退率が高い場合は、内定後のフォロー施策やコミュニケーション方法に課題がある可能性があります。
分析手法
内定辞退率を以下の計算式で算出します:
内定辞退率 = 内定を辞退した人数 ÷ 内定者数 × 100
例
内定者20人のうち5人が辞退した場合:
5 ÷ 20 × 100 = 辞退率25%
改善施策
- 内定後のフォロー体制を強化し、定期的な連絡や懇親会を実施する。
- 候補者の不安を解消するために、仕事内容や福利厚生に関する情報を具体的に提供する。
- 内定者専用のLINEグループや専用ポータルを活用して、企業への帰属意識を高める。
これらの取り組みによって、内定辞退率を低減し、採用プロセス全体の効率を向上させることができます。
採用活動のデータ分析に活用できるおすすめツール
採用活動を効果的に行うためには、データを収集・分析できるツールの活用をおすすめします。以下では、採用活動のデータ分析に役立つツールとして、「採用一括かんりくん」、「Google アナリティクス」の2つを紹介します。
採用一括かんりくん
採用一括かんりくんは、採用活動の効率化と成果の最大化を目指す企業に最適な採用管理システムです。応募者管理から内定者フォローまでを一元管理し、データをもとにした採用活動を最適化することが可能です。
主な特徴
- 候補者データ管理:応募者の選考ステータスや選考結果など、採用に関するデータを収集・ログ化できる。
- 歩留まり率の可視化:各選考プロセスでの通過率を自動で計算し、ボトルネックを特定可能。
- LINE連携:応募者とスムーズに連絡を取り合い、選考辞退や内定辞退を防ぐ仕組みを提供。
導入メリット
- 作業の自動化により、人件費を削減しつつ業務効率を向上。
- データに基づく採用戦略の改善で、費用対効果を最大化。
資料のダウンロードはこちら
Google アナリティクス
Google アナリティクスは、採用サイトのアクセス解析に特化した無料のツールです。訪問者の行動データを収集し、サイト改善や採用活動の成果向上につなげることができます。
主な解析項目
- ページビュー数や訪問者数
- 平均滞在時間や直帰率
- 流入元(検索エンジン、SNS、求人サイトなど)
- ページごとの離脱率
活用方法
- 採用サイトの訪問者数が応募数にどの程度影響しているか分析。
- 年齢層や性別ごとの訪問データを活用してターゲット層の理解を深める。
- 最も訪問者が集まるページを特定し、コンテンツを強化してエンゲージメントを向上。
Google アナリティクスを活用することで、採用サイトの課題を特定し、改善施策を講じることができます。
まとめ
採用活動において分析は、自社の課題を適切に把握することや次年度以降の採用活動をより良くしていくために重要な業務です。質の高い分析を行うには、採用活動中のデータ蓄積が必須となります。予めどういったデータを集計しておく必要があるかを確認した上で採用管理シートなどに情報を必ず入力していきましょう。
また、定量的なデータだけでなく、定性的なデータも合わせて活用することがより質の高い分析を行うことへと繋がるため、アンケートや面接官の評価内容、応募者情報などもしっかり収集していきましょう。
今回は採用活動全体の分析について紹介しましたが、下記の記事で選考中の歩留まりを改善するための方法についてまとめているので、こちらも是非、参考にしてみてください。
→採用における歩留まりを改善する方法
「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。
私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。
人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。